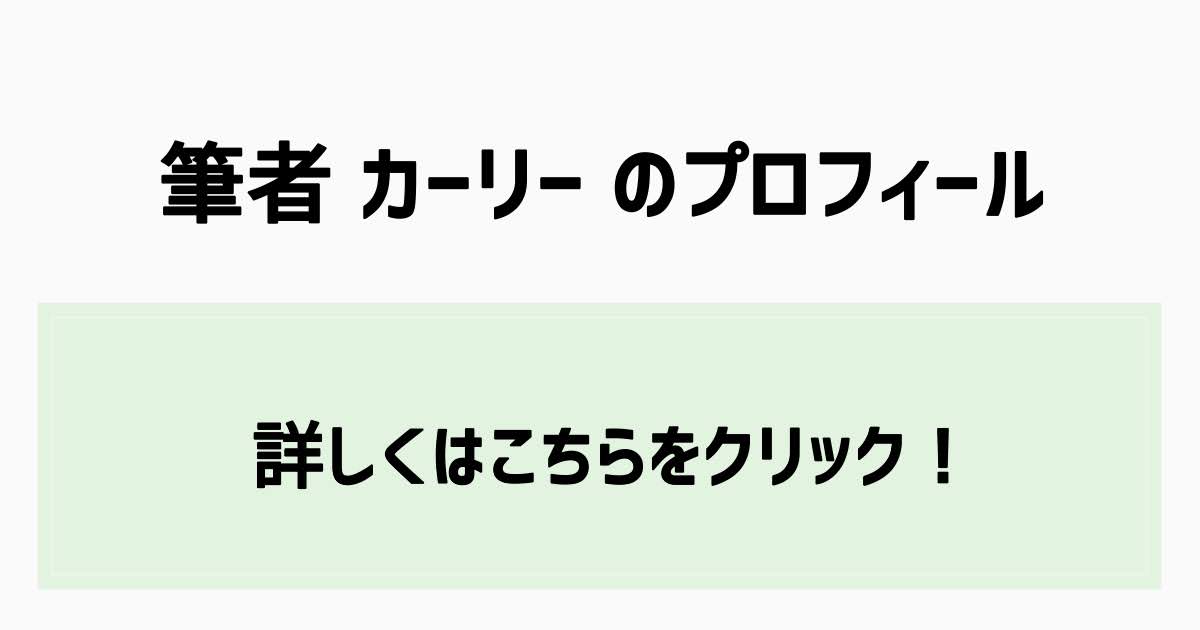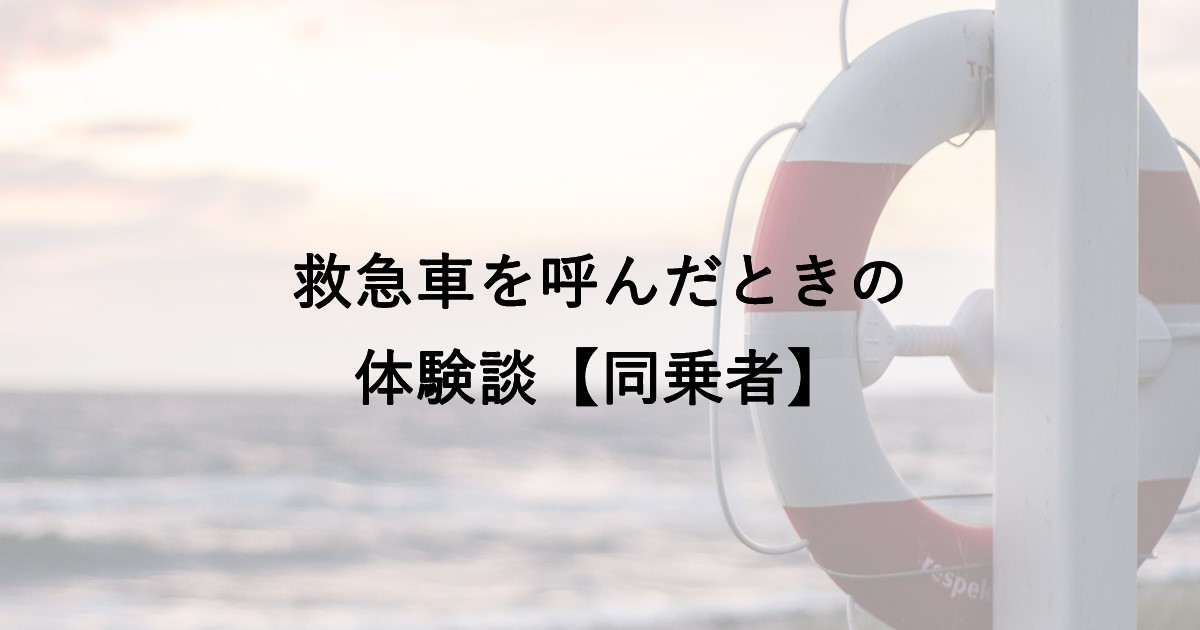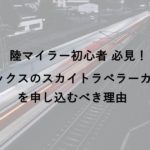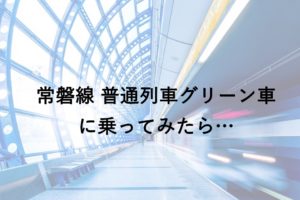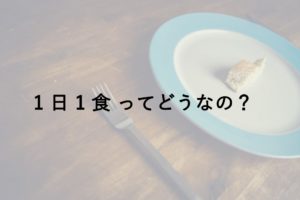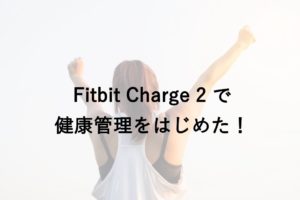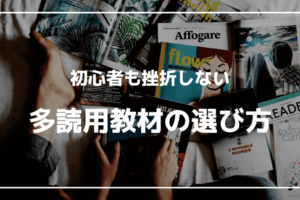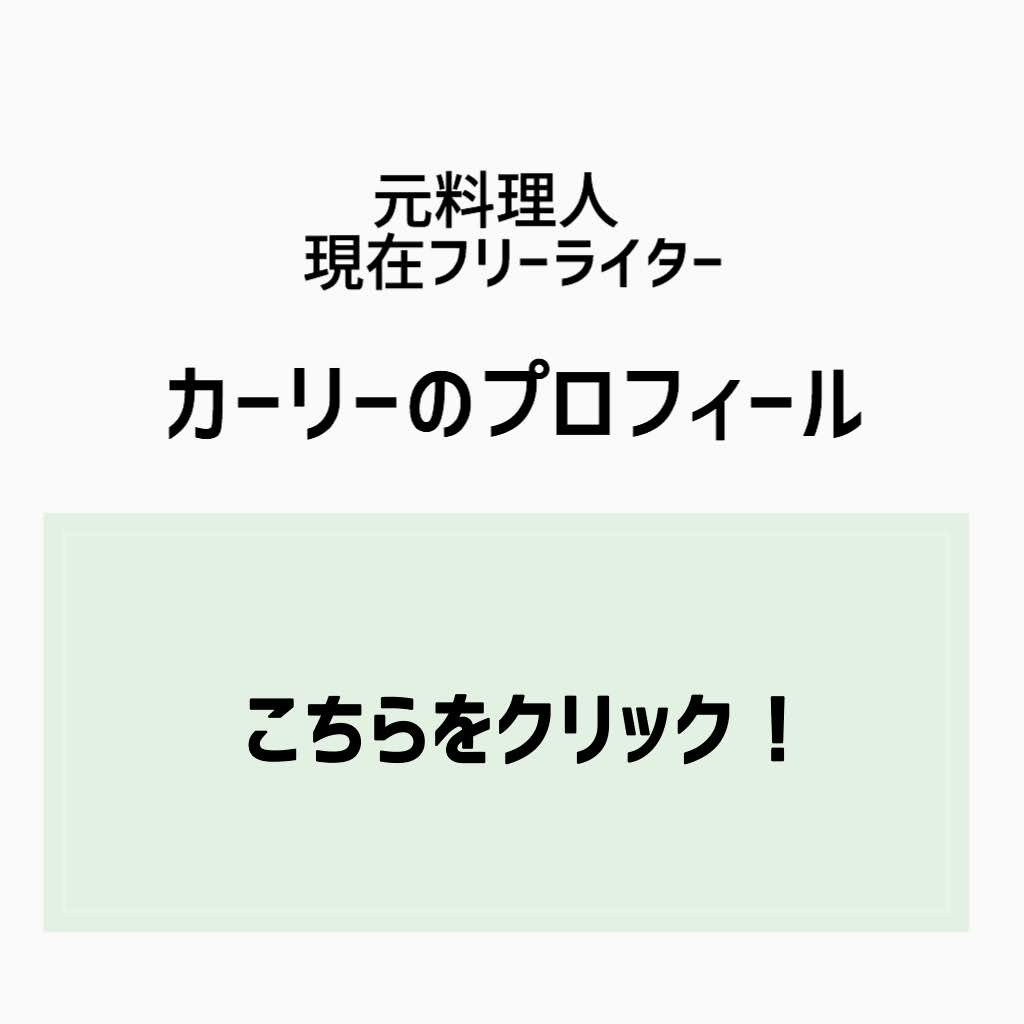三世代で暮らす carly です。
先日、夜中に家族の体調が悪くなり、救急車を呼びました。
救急車を呼ぶような場面に遭遇したのは人生で初だったので
- 軽々しく救急車を呼んではいけないという思い
- 「もし手遅れになったら?」という思い
がゴチャゴチャになり、気が気ではありませんでした。
今回はその体験を元に、救急車を呼んだことがない『救急車 初体験者』に向けて、一緒に住んでいる家族のために救急車を呼ぶときに役立つポイントをまとめます。
この記事を読んでおけば
- いざ救急車を呼ぶときにとるべき行動
- 救急車を呼ぶときのために備えておきたいこと
を把握できるので、いざというときにパニクらずに済みます。
焦るときこそ冷静に行動し、家族との穏やかな生活が続くことを願いましょう。
初めて救急車を呼んだ体験談|休日の夜中

わたしが救急車を呼ぶことになったのは、休日の夜10時くらいでした。
同居している80代の祖母の具合が悪くなったためです。
意識はしっかりしているものの、いつもより血圧が高くめまいがするとのこと。
眠れないほど症状がひどかったので専用ダイヤルに電話で相談し、救急車を呼びました。
わたしは市町村の冊子に載っている番号に電話しましたが、後から調べたら『#7119』と同じ東京消防庁に繋がっていたことが分かりました。
GW連休中の夜中|病院も夜間診療も閉まっている
連休中の夜中でしたが、幸い近くの病院で診てもらえることに。
処置と手続きが終わって家に帰ったのは、夜中の1時半過ぎでした。
今回のケースは
- 大量に出血している
- 呼吸が止まっている
のように緊急性が高いわけではなかったので、祖母もわたしも数時間で帰宅。
祖母のめまいは内耳のバランスの崩れによるものだとのこと。
原因は不明で、よく効く薬もないため、簡単に言えば『放置するしかない』という診断です。
また症状が出た場合には、今回のように点滴や服用薬で症状を抑えることしかできません。
原因を取り除けないとはいえ、死に直結しない状況であることは不幸中の幸いです。
救急車を呼んでから自宅に帰るまで約4時間
わたしが救急車を呼んでから家に帰るまでの流れは、以下の通りです。
- 相談ダイヤルに電話(#7119)
- 指示に従い救急車を呼ぶ(119)
- 救急車内からの電話を受ける
- 車内に乗り込み病院へ搬送
- 診察の受付
- 待合室で処置と診察を待つ
- 医師の診断を聴く
- 支払いと薬の受け取り
- タクシーで帰宅
今回は救急相談センターに電話する余裕がありましたが、場合によっては一刻も早く救急車を呼ばなくてはならないこともあります。
例えば、大量に出血していたり骨が折れていたり、呼吸が止まっていたりする場合などですね。
緊急性が低い今回のような場合でも、救急車を呼んでから帰宅するまでに約4時間かかりました。
平成から令和へ変わる瞬間を病院で過ごすことになるとは…
家族の具合が悪くなったときに救急車を呼ぶ手順

交通事故を除き、具合が悪い人が
- 大量に出血していない
- 呼吸がきちんとある
- 意識がしっかりしている
ような場合であれば、上記の手順を参考にすれば問題ありません。
まずは『#7119』に電話して救急車を呼ぶべきかどうかを相談しましょう。
救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときに使えるスマホアプリ
『#7119』に電話すると、混み合っていて繋がらないケースもあります。
そんなときには総務省 消防庁の『全国版 救急診断アプリ(Q助)』を使いましょう。
👉 iOs版『Q助』
👉 アンドロイド版『Q助』
画面の指示に従って項目を選んでいくと
- 今すぐ救急車を呼びましょう
- できるだけ早めに医療機関を受診しましょう
- 緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう
- 引き続き、注意して様子をみてください
のように、数秒で緊急度を診断してくれます。
質問事項はけっこう細かく設定されているので、アプリでも十分に役立つはずです。
救急車を呼ぶかどうかの判断基準|すぐに呼ぶべき症状
救急車を呼ぶ基準は、消防庁によって一例が決められています。
大人と子供別に一例をチェックしてみましょう。
【成人や高齢者】
- 血を吐く
- 突然の手足や顔のしびれ
- 突然の激しい頭痛や胸痛
- のどに飲食物が詰まった
- 意識なし、けいれん
- 大やけどや交通事故
- 強烈な腹痛や血便
- ろれつが回らずうまく喋れない
【子供】
- 交通事故
- 大やけど
- 手足の硬直
- じんましん
- 意識なし、けいれん
- 頭をぶつけて出血
- 下痢や嘔吐、血便
- 異物を飲み込んだ
- 顔色や唇の色が悪い
- のどに飲食物が詰まった
- 激しい咳やゼーゼーとした呼吸
以上のような症状は緊急度が高いので、すぐに救急車を呼んで処置してもらう必要があります。
健康な大人が見て余裕があれば、先ほど紹介したアプリや専用ダイヤルを利用しましょう。
救急車を呼んだときに聞かれること|固定電話がベスト

『119』と現場に向かっている救急隊員からの電話で聞かれることは以下の通りです。
- 具合が悪い人の年齢と性別
- 具体的な症状や血圧など
- 持病があるかどうか
- 飲んでいる薬があるかどうか
- かかりつけ医はあるか
わたしは固定電話から電話したので、住所は聞かれず『〇〇さんですね』と言われました。
通常であれば、住所や電話番号を聞かれます。
スマホから電話すると管轄外の消防へ繋がってしまい、救急車の到着まで時間がかかることがあるので注意が必要です。
なるべく固定電話で通報するように心がけましょう。
救急車に同乗する家族がすること|本人に変わって手続きなど

救急車に乗れる家族は2~3人です。
付き添いの家族は
- 病院についた後の受付
- 支払いや薬の受け取り
- 医師の診断内容を聴く
- 入院に関する手続き
- 帰りのタクシー手配
などを行い、具合の悪い家族のサポートをします。
救急車に乗る前に持っていくもの
救急車に乗るときに持って行ったものは以下の通りです。
- 保険証
- 診察券
- スマホ
- 家の鍵
- 本人の下履き
- いつも飲んでいる薬
- お金(できれば2万円くらい)
保険証やお金は、支払いや帰りのタクシー代となるため必須です。
夜間のタクシーは割増料金になりますし、車社会の場合は家から病院まで遠いことがあるので、お金は多めに持っていきましょう。
かかりつけの病院で診てもらえそうな場合は、診察券もあった方がよさそう。
スマホは時間の確認やほかの家族への連絡手段として持っていきます。
診察や処置を待つのに1時間以上かかったので、時間つぶしのための本があるとよかったです。
まあ、ほとんどの人に本を呼んでいる精神的な余裕はないと思いますが…
救急車を呼ぶそのときに備えて普段からしておきたいこと

今回のわたしのケースのように、本人がピンピンしていて緊急性が低くても、救急車となれば冷静さを失ってしまいます。
そんなときに焦ったり迷って時間をロスしたりしないためには、いざという場面に向けて備えておくことが重要です。
今回の体験を元に、わたしは以下のことを行いました。
- 保険証とまとまったお金をセットにしておく
- 『#7119』と『119』と書いた紙を電話の近くに貼る
- 住所と電話番号を書いた紙を電話の近くに貼る
わたしはキャッシュレスを心がけていますが、夜間の病院では現金のみでした。
このような非常事態に備えて、ある程度はまとまった現金を用意しておくべきですね。
救急車を呼ぶ|冷静に対処するには普段の備えから

今回は人生で初めて救急車を呼び、同乗した経験を元に
- 救急車を呼ぶときの手順
- 同乗した家族がやること
- 救急車に乗るときの持ち物
をまとめました。
わたしのように一刻を争う事態でなくとも、家族が命の危険にさらされているかもしれない状況で冷静に行動できる人は多くありません。
そんなときに迷わずスムーズに行動するには、日頃からの備えが大切です。
大切な家族との穏やかな生活を守るために、わたしの体験が誰かの役に立てばと思います。