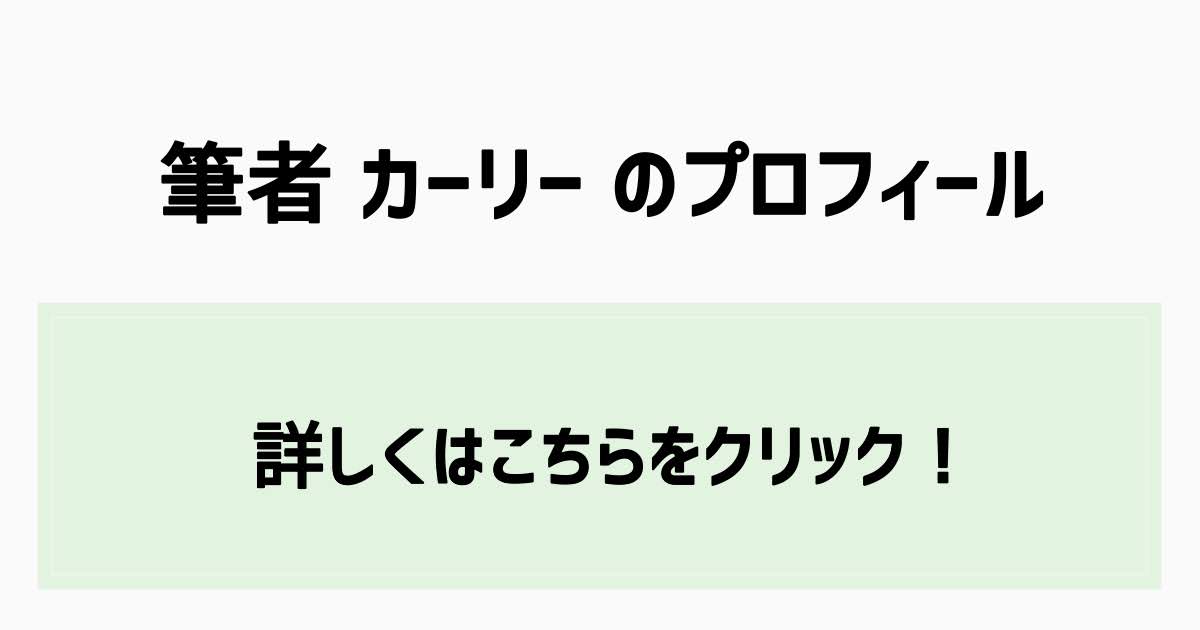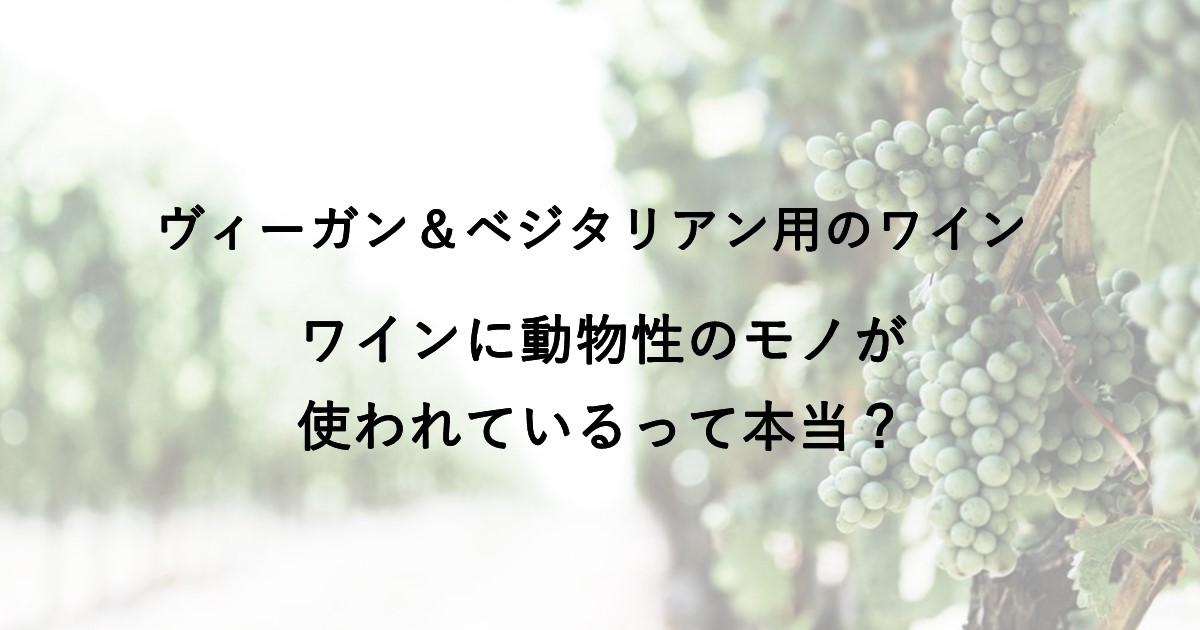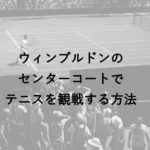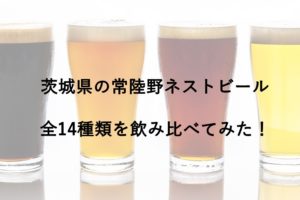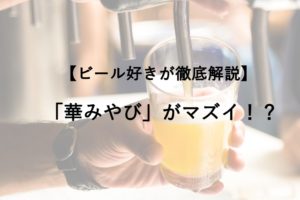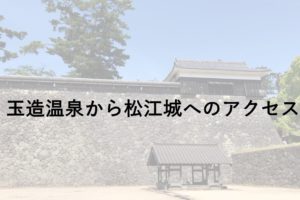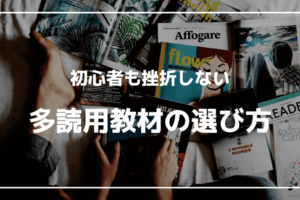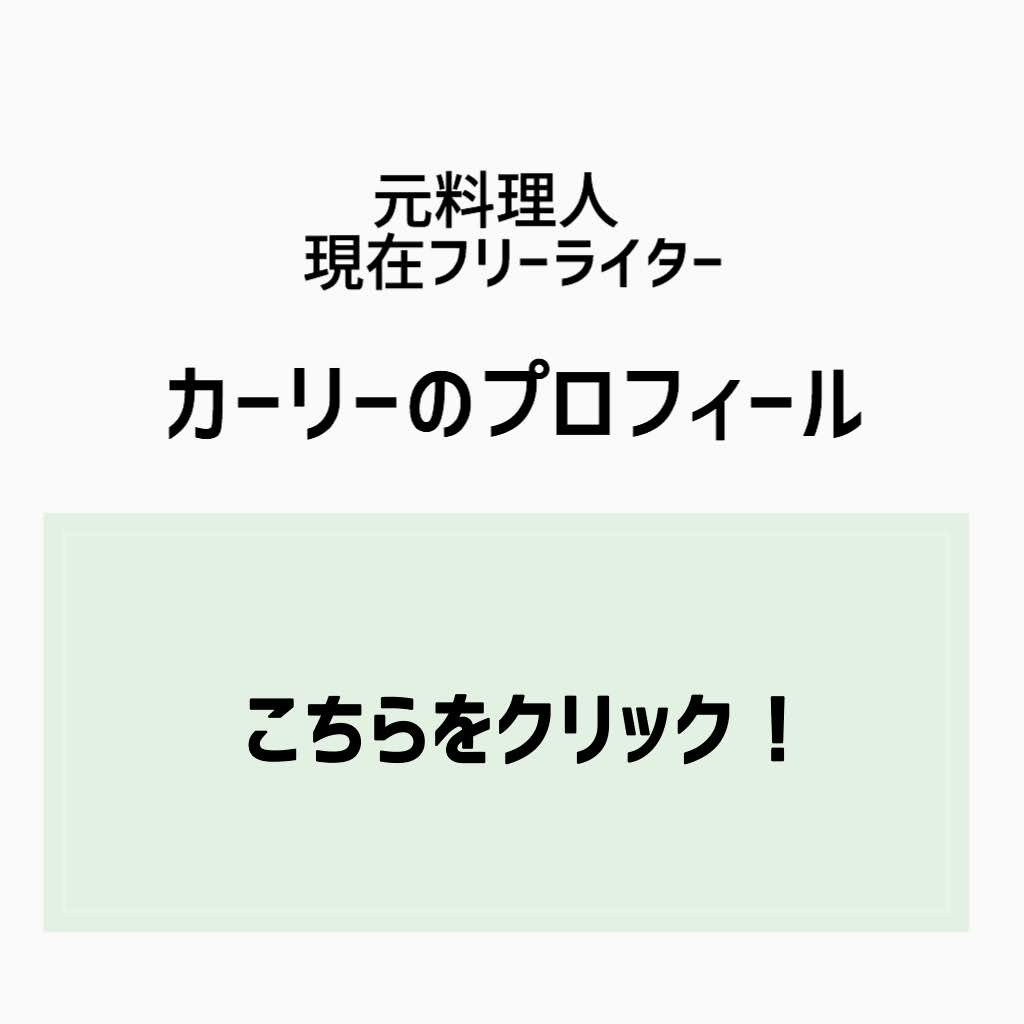元料理人のcarlyです。
今回はイギリス暮らしで発見した驚きの体験をシェアします。
それは、ワインにもヴィーガンやベジタリアン用があるということです。
そこまで配慮されたワインが売られている事実にも驚きましたが、そもそもワインに動物性食品が使われていることにビックリ。
ということで今回は、
- ベジタリアン用ワイン
- ヴィーガン用ワイン
の違いと一般的なワインとの違いについて詳しく紹介します。
ヴィーガンやベジタリアンじゃない人にも、こんな事実があるんだよというのを知ってもらえればうれしいです。
ロンドンのスーパーで菜食主義用のワインを発見

ことのきっかけは、スーパーで何気なく買い物をしていたときのことです。
わたしは普段からお酒を飲みますし最近はワインにハマっていることもあって、いつもと同じようにワインコーナーをブラついていました。
すると、ワイン棚の値札にこのような表示があることに気づいたんです。

ちょっと見づらいですが、ヴィーガンとヴェジタリアンという表示があります。
ヴィーガンのみの場合とベジタリアンのみの場合、はたまたダブルで書かれているものも。
それに加えて、
- オーガニック
- バイオダイナミック
- 低SO2
という表示がされているワインもありました。
こちらもひとつだけの表示があるものや、いくつか同時に表示されているものもあります。
ロンドン(イギリス)だけでなくヨーロッパは日本よりも食に関する意識が進んでいることは知っていましたが、日本では一切みかけない表示に驚きまくりです。
しかも、ワインコーナーの半分近くがこのような表示で埋め尽くされていて、それはそれはもう衝撃でした。
ヴィーガンは一般的なワインを飲めない

このような体験をしてみてはじめに思ったことは「そもそも普通のワインって動物性のモノなんて入ってるの?」ということ。
ワインがぶどうからつくられるのは当たり前ですが、ぶどうは植物性だから問題なしです。
酵母を入れてワインを発酵させますが「酵母は動物なのか?」というとかなり疑問。
そこで詳しく調べてみると、一般的なワインをつくるときはろ過の際に動物由来のフィルターを使うんですって!
つまり、動物性のモノを一切とらないヴィーガンは一般的なワインが飲めないということです。
この動物由来のモノを「清澄剤(せいちょうざい)」といいます。
主な原料は動物のコラーゲン(ゼラチン)や卵白など。
たしかに、フランス料理では「コンソメ」をつくるときに液体を澄ませる役割として卵白を使うので、首がもげるほど納得しました。
ヴィーガンまたはベジタリアン用のワインではこれらの代わりに
- 鉱物由来の粘土のようなもので代用
- 珪藻土で代用
- 無濾過
- 植物由来のたんぱく質で代用
という方法でワインを完成させています。
動物由来のゼラチンや卵が入っていないので、ヴィーガンの人でも飲めるということですね。
ヴィーガン用ワインとベジタリアン用ワインの違い
ベジタリアン用ワインとヴィーガン用ワインにもちょっとした違いがあります。
結論から言うと、ベジタリアン用ワインには卵白が使われている可能性があるということです。
先ほど、ヴィーガン用ワインには
- 動物由来
- 卵白
といった清澄剤が使われていない、と述べました。
ヴィーガンは動物性食品を一切とらないので、卵も食べません。
しかし、ベジタリアンは卵は食べるので、ベジタリアン用ワインには卵白が使われているかもしれないってことです。
つまり、ヴィーガンの人はベジタリアン用ワインは飲めないということ。
このようなことが一般的に起こるので、ロンドンではもちろん海外では
- デイリーフリー(乳製品なし)
- ヴィーガン向け
- ベジタリアン向け
- グルテンフリー
- シュガーフリー
- エッグフリー
といった食品表示をレストランや屋台、お菓子屋やパン屋などいたるところで目にします。
ヴィーガン用ワインとビオワインは違う?

〇〇用ワインなどというと、いろいろな言葉が思い浮かびますよね。
先ほども少し触れましたが、
- ベジタリアン用ワイン
- ビオワイン
- オーガニックワイン
など、ワインだけでもこれだけの「体にやさしそう」なワインがあります。
とくに分かりにくいのがオーガニックとビオの違いでしょうか。
それぞれ詳しくまとめてみますね。

ビオワインとオーガニックワインの違い
日本では細かな違いが知られておらず、ほとんどの人は同じものだと思っているかも。
ビオワインとは「ビオディナミ製法」でつくられるワインのことです。
ビオディナミ製法とは「ビオロジック製法」という有機農法に月や星座、引力などのスピリチュアルな要素を組み込んだつくり方のことをいいます。
ビオロジック製法が、日本でいう「オーガニック」に一番近いですね。
ぶどうを育てる段階から農薬や化学肥料を一切使わず、ワインをつくる過程においても添加物に厳しい決まりがあるのがビオロジック製法。
かなりややこしい話ですが、日本でいうオーガニックワインはビオロジック製法でつくられたワインのことを指します。
一方のビオワインは、海外でいうバイオダイナミックワインのこと。
ビオディナミ製法という有機農法にスピリチュアル要素をくわえた方法でつくられたぶどうを使ってつくるワインのことです。
同じようにしか思えないこの2つのワインは、ぶどうの育て方とワインをつくる過程にちょっとした違いがあるということですね。
ヴィーガン用ワインとビオワインの違い
先ほど説明した
- ビオワイン(バイオダイナミックワイン)
- オーガニックワイン
の違いがわかると、このナゾも解けるのではないでしょうか。
ヴィーガン用ワインもビオワインも、つくる過程に焦点が当てられているという点は同じです。
しかし、ヴィーガン用ワインは必ずしもビオワインやオーガニックワインではないし、逆にオーガニックワインやビオワインがヴィーガン用ワインだとは限りません。
わたしがスーパーで撮ってきた写真をみると…


- バイオダイナミックのみ
- バイオダイナミック+ヴィーガン
- オーガニック+ヴィーガン
- ベジタリアンのみ
という表示が確認できます。
つまり、自分が求めるワインを買うには表示をみて選ぶ必要があるということであり、選ぶための知識が必要だということです。
決してヴィーガンやベジタリアンが良い!と言うつもりはなく、日本人には自分が必要な物を選んで食べるという感覚が足りない。
環境や「当たり前」という固定概念にとらわれて、選ぶことや知識を身につけることを怠ってはいけない。
切にそう思います。
ワインで感じた「食のボーダーライン」

ロンドンもといイギリス、はたまたヨーロッパではヴィーガンやベジタリアンという価値観がごく一般的なものであるということは、無関心だったわたしでも知っていました。
しかし、ワインにも
- ヴィーガン用やベジタリアン用
- オーガニックやビオディナミ
など、知らないことだらけだったことには驚いています。
このような表示がされていることで自分が求める「食」を選びやすくなるし、どんな人でも「食」を楽しめるようになるはず。
海外では陸続きという土地柄、いろいろなものに国境がなくなっています。
移民のように人種や国籍なんかも関係なくなって、個人が尊重されたり多様性を認めたりすることが当たり前のヨーロッパ。
わたしはロンドンに住みながら「食」を通して、日本には
- 少数派なモノには目をつぶりたがる
- 違いを受け入れられない
- 理解できないものは受け入れない
という問題があると感じています。
ヴィーガンやベジタリアンにしてもそうで、まだまだ偏見があるのではないかと。
行動に移すか移さないかは問題ではなく、
- そういった考え方があるんだ
- みんなそれぞれの価値観で生きていていいよね
と受け入れるだけでいいのになと思います。