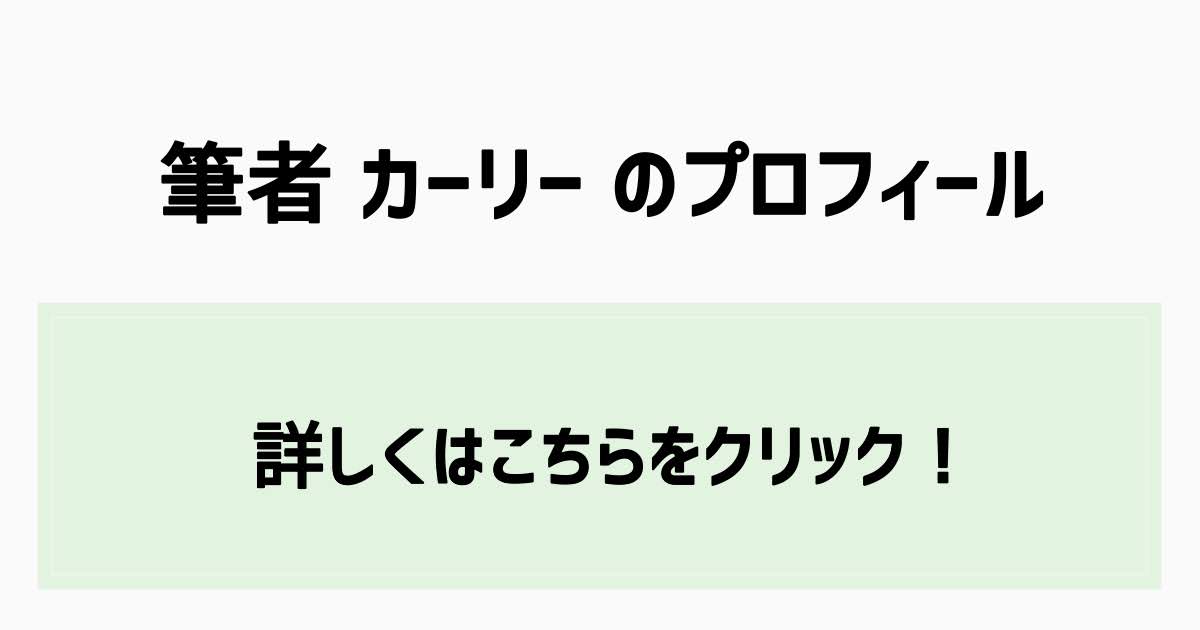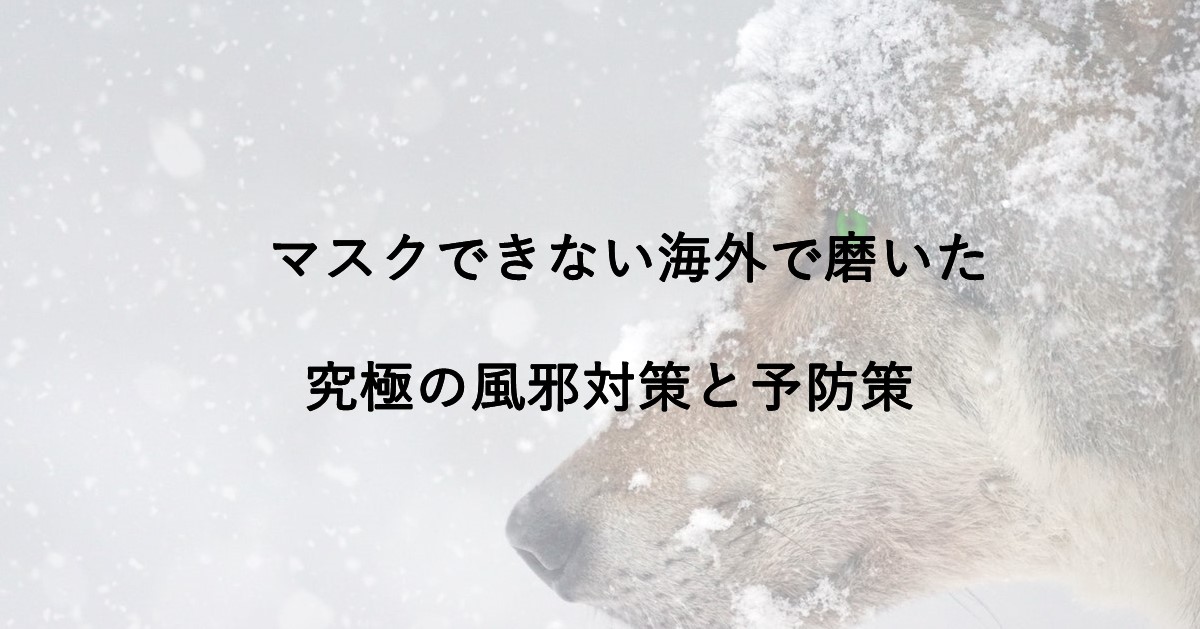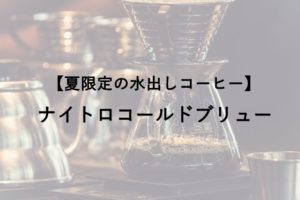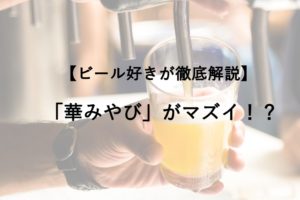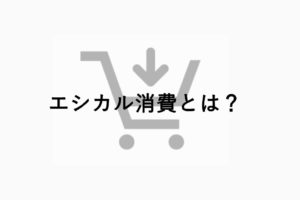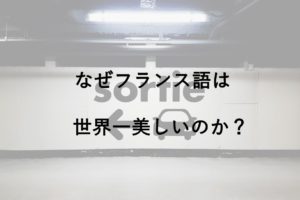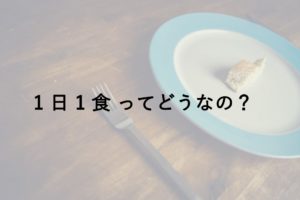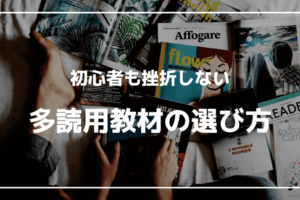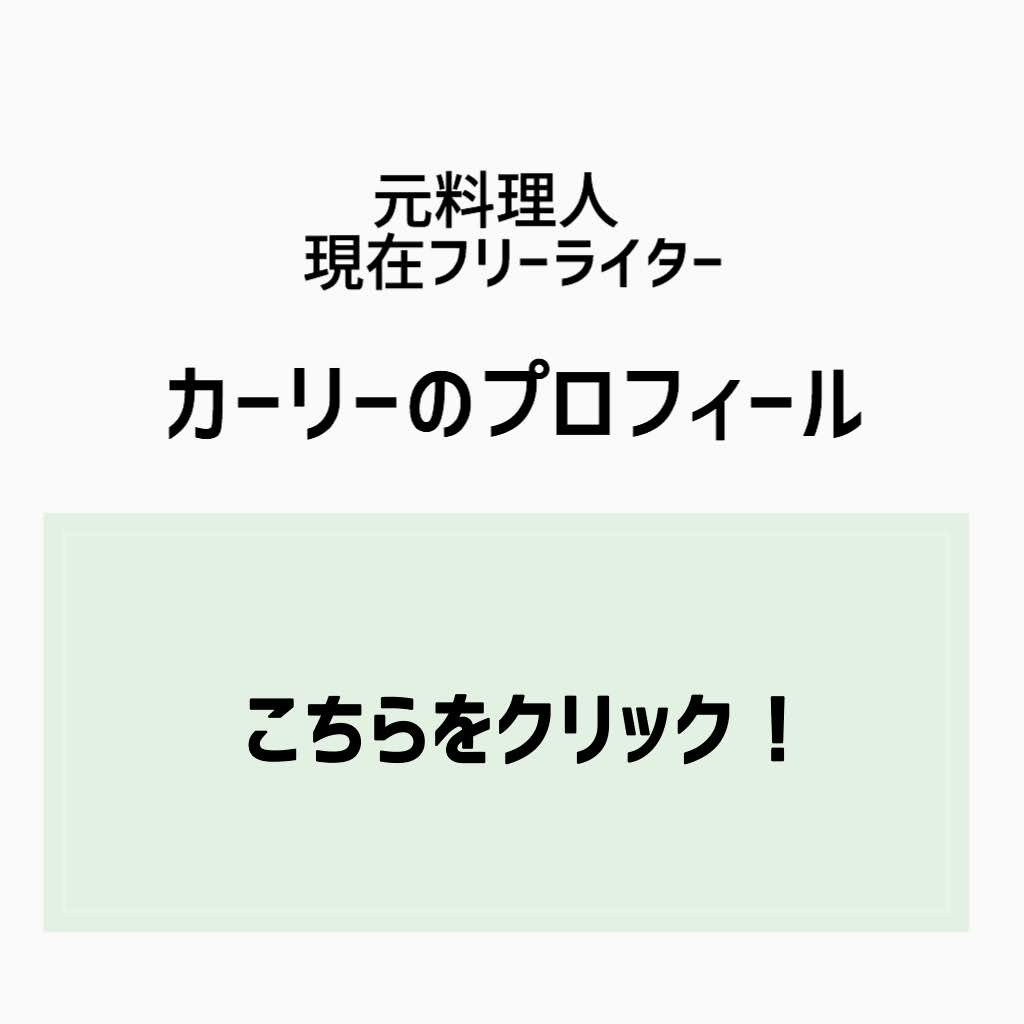フリーライターのcarlyです。
- うがい手洗いなどの基本的な予防策も心がけている
- 睡眠と栄養などの体づくりは万全
なのになぜか風邪を引いてしまう… と悩んでいませんか?
どんなに気をつけていても風邪を引いてしまうの、なんでなんでしょうね。
わたしは万全の対策をしたのにも関わらず月に5回も風邪を引いたので、風邪はもはやUMA以上の謎だと思っています。
そんなわたしが執念で調べ尽くした『風邪』について。
ゼッタイに風邪を引きたくない人は、こちらの記事を参考に
- 人間ができる最大限の風邪予防対策
- いざ風邪を引いてしまったときの対処法
を実践してみてください。
うっかり引いちゃう風邪を防ぎ、もし風邪を引いてしまってもスピーディーに対処する方法を心得ておきましょう!
風邪は病気ではない?

そもそも、風邪というのは病気ではありません。
風邪はウイルスによって引き起こされ、医学的に「上気道感染症」と呼びます。
「症」という漢字をみても分かる通り、風邪はその症状が出ている状態のことを指すんですね。
病院で「風邪です」と診断されることはあっても、実は
- 軽めの発熱
- のどの痛み
- 鼻づまり
- 鼻水
- せき
- たん
- 頭痛
というような「症状」を分かりやすく伝えるためにまとめて「風邪」と呼んでいるだけであって、病気ではないということです。
風邪って年中引くのでお医者さんからしたら「ただの風邪です」とひと言で伝える方が楽だし、患者さんにとっても分かりやすいですよね。
風邪は体の防御反応
じゃあ「なぜ鼻水が出たり熱が出たりくしゃみやせきが出たりするの?」って感じですよね。
風邪は
- アデノウイルス
- ライノウイルス
- コロナウイルス
といった「ウイルス」が原因で症状が引き起こされます。
よく「風邪菌が移る!」とかいいますが、黄色ブドウ球菌のような細菌ではなく、上記のようなウイルスのことを指しているんです。
空気中に漂う風邪のウイルスを吸い込み、鼻やのどの粘膜にくっついて増殖すると、ヒトの細胞を攻撃し始めます。
これが「炎症」というもので、炎症が起こると様々な風邪の症状が出るんです。
そして人間の体の中では免疫機能が働いて、ウイルスを外に追い出そうと活発化します。その活発化した状態が、以下のような症状として現れるということ。
-
熱が出る・・・ウイルスが活動できない温度まで体温を上げる、免疫機能を活性化する
-
のどが赤くなって腫れる、痛み・・・免疫細胞である「白血球」を血液に乗せて送るため、のどの毛細血管を広げた結果、血流が増えてのどが赤くなったり腫れたりする。危険信号として痛みが出ることも
-
せきやたん・・・のどの粘膜が炎症を起こすと、異物を排除しようと粘液がたくさん出るため、たんになる。たんが増えると、排出しようとしてせきが出る
-
鼻水や鼻づまり・・・鼻の粘膜が炎症を起こすと、ウイルスを排除しようと鼻水が出る。脳に危険信号が送られてくしゃみが出たり、毛細血管が広がって鼻づまりが起こったりする
このように、風邪の症状はウイルスを殺したり体の外に出したりするための重要な働きなので、薬を飲んで強制的に症状を抑えるのはよくないらしいです。
「風邪を引いたら早く薬を飲む」は間違い

実際に西洋では、風邪を引いたら薬で症状を抑えるということをせず、
- 栄養をしっかりとって休んだり
- ハーブティーで自然治癒力を高めたり
するなど、体の自然な防御システムに任せるのだといいます。
ちなみに「薬」というのは、一般的なベンザブロックとかコンタックとかいうやつです ↓
最近は日本でも「風邪を引いても薬を飲むべきではない」という意見を目にするようになりましたが、実践している人は少ないのではないでしょうか。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] 日本人はちょっとの風邪では休みませんからね。[/speech_bubble]しつこい鼻水や微熱なら薬で症状を抑えて仕事へ行く、という人の方が多いでしょう。
風邪ウイルスを職場や公共の場に撒き散らして、みんなに迷惑をかけているというのに。
しかし、風邪の症状が出ているということは、体がウイルスを吐き出そうと必死に働いている証拠。
そこで薬を飲んでしまうとせっかくの免疫機能が止まってしまい、いつまでも体のなかにウイルスが残っている状態が続くのです。
仕事を休めないのはよく分かります。
薬を飲むと一時的に症状が抑えられるので、元気に仕事に行けてしまいますよね。
しかし、それは結果的に風邪の治りを遅らせていることなので、余計に自分が苦しむことになります。
本来ならウイルスを排除するために全力投球すべきなのに、ムリに仕事をして余計な体力を使っているので、免疫力は持っているすべての力を発揮できませんよね。
だから、きちんと風邪を完治させたければしっかりと休んで、免疫細胞がウイルスと集中して戦える環境を整えてあげなければならないのです。
使い方によっては薬はアリ
というわたしは、少し前までは「風邪を引いた気がしたらすぐ病院へ」派でした。
- 仕事は週に1回しか休みがなく
- 休憩中や退社後に病院に行ける職種でもなく
風邪なのに39度オーバーの熱を出すような体質だったからです。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] お医者さんに「総合かぜ薬じゃなくて抗生物質を」と迫るほど。[/speech_bubble]休んでいられないので、早く治したいという気持ちと悪化したときのために、多めに薬を処方してもらっていました。
といいつつ、抗生物質は風邪ウイルスには効き目がないのだそう。
でも今思うのは、昔からよく風邪を引いていたのは病院でもらった薬で症状を抑えたことに満足して、予防を怠っていたからかもしれません。
風邪について詳しくなった今なら、すぐに薬を飲むという選択肢はなくなりました。
「よっぽど症状がひどくて、寝てもいられないという場合に薬を飲んでぐっすり眠る」という使い方ならアリかなという感じです。
やっぱり、体の自然な働きを科学的な物質で止めてしまうのは理にかなっていませんよね。
死にはしなくとも薬は体にとっては異物ですし、体に負担がゼロかといえばそうではないでしょう。
昔はまったく理解できなかったのですが、一定数いる「薬がキライ」という人の気持ちが分かった気がします。
重症化させたくない、早く治したい場合には?

- 病院に行って薬を処方してもらったり
- 薬局で総合かぜ薬を買ったり
することはなくなりましたが、それでも症状をほったらかして置くのも辛いです。
くしゃみやせきが頻繁に出るようだと家族に移してしまわないか心配だし、鼻水は汚ないしかみ過ぎて鼻が痛くなる。
鼻づまりは単純に苦しいし、熱が出ていると頭も痛くて単純にツラい。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] わたしはこのような場合には漢方を飲みます。[/speech_bubble]顆粒タイプで溶けやすく、即効性がある気がするんですよね。
漢方と薬の違いは「なにを解決するか」
漢方は薬と違って科学的なものではなく、
- しょうが
- 陳皮(ちんぴ)
- クコの実
- 甘草(かんぞう)
- 桂皮(けいひ)
などに代表される、植物由来がほとんどの「生薬(しょうやく)」からつくられます。
「しょうがは冷え性にきく、体を温める効果がある」のように、生薬が持つ力をいくつか組み合わせて体の異常を改善するのが、漢方の考え方です。
漢方の中には、
- 肩こり、五十肩
- 神経痛、関節痛
- 冷え性、生理痛
- イライラ、不眠症
- 肌荒れ
- 疲れやすい、貧血
- 頻尿、残尿感
- 肌のカサカサ、湿疹
- 鼻づまり、慢性鼻炎
- むくみ、めまい
- 足腰のしびれ、痛み
など一部ですが、このような症状ごとに漢方が用意されています。
症状の組み合わせによってブレンドする生薬が変わるので、漢方の数も無限大です。
ただ、
- 漢方を飲んでもすぐに症状が改善されなかったり
- 効果を感じられなかったり
することが多々あります。
それはなぜかというと、漢方は薬と違って症状をなくすのではなく、症状の原因を解決するために体質を改善することが目的だからです。
薬は即効性があって病気が治ったり悪いところが消えたりしたように感じますが、一時的に症状を抑えているに過ぎないので時間が経てばまた症状が現れます。
その症状を引き起こす原因を取り除けていないからですね。
一方の漢方は、
冷え性を改善したいのなら血流をよくするために血管を広げるなど、症状を元から改善して同じ症状に悩まないようにするんです。
- 薬 → 一時的に冷えをなくす(発熱させるなど) → 薬が切れれば、再び冷えの症状が出る
- 漢方 → 冷え性の原因である血流の悪さを改善する → 体質が改善されれば、時間が経っても症状は出ない
このように、薬は一時的な悩みをすぐさま解決してくれるので非常に助かりますが、何度も何度もお世話にならなければなりません。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] まさに使い捨てホッカイロのような感じ。[/speech_bubble]しかし漢方は、症状の原因をなくすために体をゆっくりといい状態に持っていきます。
そのため即効性はありませんが、最終的には漢方を飲まなくてもよくなるのです。
ただし、生活習慣が原因の場合、習慣を直せなければまた同じ症状に悩まされますが。
- 薬は原因を解決するものではなく、症状を解決するもの
- 漢方は原因を解決するが、症状の解決はゆっくりであることが多い
このように覚えておきましょう。
風邪の症状におすすめの漢方

上記で薬と漢方の違いを説明しました。
漢方が自然のもので体に優しいのに対し、薬は科学的な物質で体の反応をすばやく変えることが目的である、ということが分かっていただけたでしょうか。
では、肝心の「風邪」の話に戻したいと思います。
実際にわたしが常備しているのは「クラシエ」の以下の漢方、かぜシリーズです。
いずれも眠くなる成分が入っていないのがありがたい。
どうやら漢方は、その人に合う合わないが大きく関わっているらしく、相性がよくないと生薬が十分に力を発揮できないのだとか。
かといってすぐに効果が出るわけでもないので、症状の改善が実感しにくくて続けられないという人が多いようです。
少なくともわたし的には上記のクラシエの漢方シリーズは、風邪の症状にはすぐに効果が出ていると実感しています。
「風邪」という漠然としたイメージではなく、今回の風邪は鼻づまりがひどいなと感じたので小青竜湯を飲む。といった感じです。
特にひどくて辛い症状をピンポイントで潰していく、というアプローチが漢方の効果を実感しやすくしているのかもしれませんね。
風邪の引きはじめには「葛根湯」が効く
漢方は即効性がないといいましたし、化学物質ではないので風邪のウイルスを殺す力も持っていません。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] なのにナゼ「風邪の引きはじめには葛根湯!」というのでしょう。[/speech_bubble]漢方の一種である「葛根湯」の効果はいたってシンプルです。
風邪のひき始めに葛根湯を飲むと、ちょっとした違和感なら、葛根湯の症状を抑える成分によって風邪が進行しなくなります。
- ちょっと寒気がするかも
- のどがちょっとおかしいかも
- 鼻がムズムズする
という状態で飲むのがベスト。
それ以上、風邪が進行して症状が本格的に出はじめてしまうとすぐに治すのは難しいです。
多少であれば、風邪が悪化したときに飲んでも効果はあります。
葛根湯の主な成分は大きく、
- 鎮痛作用
- 発汗を促進、解熱作用
の2つに分けられます。
熱を出してウイルスを殺しやすい状態にするので、なにもしないよりは体の免疫機能が活性化されるということですね。
なので「風邪のために漢方薬を常備したい」という方には、
- 万能に働く
- 飲みやすい錠剤タイプ
の【第2類医薬品】葛根湯エキス錠クラシエ 240錠をおすすめします。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] ただひとつ付け加えると、葛根湯はエゲツない不味さです。[/speech_bubble]
大事なことなのでもう一度いいます。
大の大人が「ぐわああァァァ」と叫ぶほどの不味さです。
アゴが震えるほどの不味さに、わたしは顆粒タイプの葛根湯は飲まないことにしています。
どうしてもというのなら液体タイプ(【第2類医薬品】本草葛根湯シロップ 30mL×3)を。
顆粒タイプは飲むのに失敗する確率がとても高く、失敗するとマズい顆粒がいつまでも口の中に残るので、生きた心地がしません…
でも、飲むタイミング(超初期段階)を間違えなければ、葛根湯はかなりの力を発揮してくれますよ。
葛根湯がイヤならば、ゼナジンジャーがおすすめです。
値段が高いだけあって、こちらもタイミングを間違えなければ効果バッチリ。
お守り代わり、安心材料として常備しています。
風邪はいつ、どのタイミングで引くのか?

ここまでは、
- 風邪のメカニズム
- 薬と漢方の違い
- おすすめの漢方
を紹介してきましたが、一番大切なのは「風邪を引かないこと」ですよね。
漢方を常備しているわたしですが、風邪を引きたくない!と思って様々な対策をしてきました。
しかし、あえなく失敗。昨年ひと月に5回も風邪を引いた教訓を活かしきれませんでした…
- 家では2~3時間に一回、手洗いうがい → アルコール
- 外出先では30分に一回、手洗いうがい → 発見するたびアルコール
- こまめに飲み物を飲む(緑茶がおすすめ)
- 飲み物がないときは、ガムやアメで対処
とくに手洗いうがいに関してはこれまでの人生で一番回数を増やしたし、時間をかけて「そこまでするか!?」というレベルで行っている自信があります。
最近は外出先でもアルコール消毒をよく目にするようになりましたし、家にもポンプ式のアルコールを設置しました。
スーパーやショッピングセンターの消毒液は、たぶんほとんどの人が使っていないからだと思いますが、結構な確率で空になっているのでイラッとします。
※余談ですが、食中毒が気になる方へ。
冬に増えるノロウイルスはアルコールでは殺せないので「ノロパンチ」か「手ピカジェル プラス[指定医薬部外品]
」にしましょう。
こんなにも全身全霊で風邪対策をしたにも関わらず、風邪をひいたのです。
もう腹が立って仕方がないのでこの記事を書いたわけですが、一番気になったのは
- こんなにも予防策をしているにも関わらず風邪を引くというのなら、いつどこで風邪菌が体に入ったのか
- はたまたいつどのタイミングで発症したのか?
ということです。
睡眠時は免疫力が下がっているため、最も風邪を引きやすい時間
基本的に人間が寝ている間は免疫細胞が活発に働けないので、免疫力が落ちている状態なのです。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] しかも冬は部屋全体が乾燥しまくっています。[/speech_bubble]寝ていると水分を取れないのでさらに口の中が乾き、ウイルスが粘膜にくっつきやすくなる。
この状態が最も風邪を引きやすいのだということです。
これは盲点でした…!
寝るときの状態を整えることで風邪予防
やはり、風邪を引かないようにするには、乾燥対策を行うのが効果的だと予測できます。
できれば加湿器などで部屋全体の湿度を上げて、ウイルスが活動しにくい環境をつくるとよいです。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] 湿度が上がれば乾燥からノドを守れるので一石二鳥![/speech_bubble]わたしはしていませんが、寝るときに暖房をつける派の人はとくに気をつけるべきポイント。
マスクなどをして寝るという方法もあると思いますが、起きたときに行方不明になっている確率の方が高くないですか?
「のどぬ~るぬれマスク 就寝用」は試してみたいと思いますが、寝るときはやめておきます…
◇飛行機の中では本当におすすめです!>>>>ヨーロッパ・飛行機の乾燥対策に必須!就寝用ぬれマスクで風邪引かず
あとは寝室や寝具をこまめに掃除して、ホコリなどをなくしておくのも大切。
細かいハウスダストなどが体に入ると、アレルギーでなくても体が反応してしまうので、風邪のウイルスがやってきても対処しきれないのです。
乾燥にくわえて免疫力が低下している時間なので、寝ているときは風邪ウイルスにとっては最もオイシイ時間。
いざ風邪ウイルスが体に入ってきても、少しは抵抗できる力を残しておくのが大切ですね。
当たり前ですが、寝ている時間は免疫力が低いとはいっても、睡眠時間を減らすことは根本的に免疫機能を低下させてしまいます。
風邪予防には、栄養バランスのとれた食事と十分な睡眠をとることが大切です。
これだけは押さえたい3つの風邪の予防法

わたしがこれまでに風邪を引かないために行ってきた予防法と、イラ立ちながらも風邪について研究したことによって「完全版の風邪予防術」を考えました。
栄養をしっかりとってよく眠る、適度な運動をするといった基本的なことを踏まえた上で実践することが前提です。
運動して筋肉をつけることで基礎体温が上がるので、ちょっとやそっとの風邪ウイルスなら悪化する前に治せてしまいます。
①手洗い・うがいをこまめに
専門家も推奨しているのが「手洗い・うがい」です。
食中毒と同じで「つけない・増やさない・持ち込まない」が基本ですよ~。
◆明治の「手洗い・うがい」のススメの「ムービー」を見てみてください。
これを見ると、自分がいかにテキトーに手洗い・うがいをやっていたかわかるでしょう。
うがいのときは「あいうえお」をいいながらガラガラすると、口の中の全方向のウイルスを洗い流せるのでおすすめ。
挙げたらキリがないのですが、
- パソコン
- スマホ
- ドアノブ
- 吊革
- 手すり
- エレベーターのボタン
- お金
このように、至るところにウイルスがついている可能性があるので、トイレにいくたびに石鹸で手洗い → きれいな手でうがいをしましょう。
トイレから出たときに手を水だけでチョチョッと洗う人が多いですが、あれは逆に菌やウイルスを増やしていると科学的に証明されています。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] 手洗いは必ず石けんをつけましょう![/speech_bubble]わたしは外出先ではトイレに行きたくなくても、トイレを発見する度にうがいをしに行っていました。
だいたい30分に1回くらいのペースでしょうかね。
これくらいやっても風邪を引くので、やり過ぎくらいやらないと効果が薄いと思います。
②のどの乾燥を防ぐためにこまめに水分補給
こちらもお医者さん推奨の方法で、のどが乾燥するとウイルスが喜んでしまうので乾燥しない環境をつねに保つことが大切。
緑茶のもつカテキンが風邪ウイルスに効果的で、ある病院の先生は患者さんを一人診るごとに緑茶を2口くらい飲むそうです。
わたしもロンドン在住のときに実践しましたが、これが一番意味ある風邪予防だと思います!
(ロンドンでは「マスク=超危険な感染症患者」なので、これしか予防策がない)
これなら家でも職場でも、外出先でも気軽にできそうですよね。
飲み物が飲めない場合は、アメやフリスク、ガムなどで唾液を出すとよさそう。
「ウイルスが体に入ってしまって大丈夫?」と心配する方も多いと思いますが、胃液などでウイルスは死んでしまうので心配ありません。
大切なのは、
- 粘膜でウイルスが増えるのを防ぐ
- 乾燥を防いでウイルスが活動しにくい環境をつくる
以上の2点です。
ウイルスが増える前に、飲み物で胃の中に流し込んでしまえばオッケーということですね。
③寝るときは部屋が乾燥しないようにする
加湿器があればいいのでしょうけど、新しいものを買いたくないなぁと思う方もいるでしょう。
わたしもモノをあまり増やしたくないタイプなので…
▲といいつつ、爆売れしているというネコの加湿器が気になっている…
空焚き防止がいいですよね。
加湿器がないという場合には、濡れたタオルを何枚か干しておくのがおすすめです。
朝になったらカラッカラに乾いているので、ボディタオル3~4枚は干しても大丈夫。
そしてできれば、寝る部屋で暖房をつけるのは避けた方がよさそうですね。
どうしてもという場合には、沸かしたお湯を洗面器にはるなど対策を行うべきでしょう。
ちなみにわたしは今後「電気ケトルを使って寝室の湿度を上げる作戦」をやってみようと思っています。
電気ケトルってお湯が沸いたときにフタを開けておくと、沸騰が止まらないって知っていましたか?
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1carly.jpg” name=”carly”] お湯が飛び散って危険なので、注意してくださいね。[/speech_bubble]かなりの勢いで沸騰し続けるので、湯気がスゴイことになるんですよね。これを応用してみようと。
これからは寝る前にケトルを持ち込んで、部屋の湿度を上げてから寝てみます。
風邪に最も効果的な対策は「乾燥予防」である

さて、風邪を引かないために最も大切なことは「乾燥させない」ということです。
のどはうがいや飲み物でうるおいを与えられますが、鼻は意外と盲点なのでは?と思います。
のどや鼻の奥を湿らせるという意味ではマスクの利用もアリですが、基本的に横や上からウイルス入り放題ですからね。
マスクをしていれば風邪やインフルエンザにはならない!と思っている人は要注意です。
今は「ハナノアシャワー 痛くない鼻うがい」などもあるので、そちらも併用するといいのではないでしょうか。
後から発見しましたが、コチラの書籍に激しく同意しているので紹介しておきます!
といいつつも、あらゆる対策を行っても風邪を引くことはありますよね。
疲れて体が弱っていたり栄養が偏っていたりすれば、いくら対策を行ってもウイルスと戦えないのですから。
そのときは薬を飲んでもいいけれど、基本的にゆっくり休むことが必要だということは覚えておかなければなりません。
唯一、服用系でオススメするのは「風邪をひくかもしれない」と思ったときに葛根湯を飲むことです。
そして万が一、症状が出て辛いというときにはかぜに効く漢方を飲んで、しっかり休息をとりましょう。
風邪は安静に寝て休めば、1週間から10日で症状はよくなるものだそう。
そこでムリして仕事に行けば、長い場合で3週間以上も長引くこともあるのだといいます。
どのような方法を取るにしても、結局はしっかりと休んで自然な免疫機能がウイルスに勝つのを待つしかない、ということなのですね。
わたしには適度な運動が一番の課題かなと思うのですが…
ただ、冷え性ではありますが基礎体温はアホみたいに低くありません。
筋肉は少ないけど基礎体温はそこそこある。けれど冷え性… 風邪はよく引く。
なんだか頭の中ゴチャゴチャになってますが「低体温と免疫力が低いのって本当に関係あるの?」と疑ってしまう状態です。
ということで、長くなりましたが風邪についての恨みツラミはここで終わりです!
お子さまでも飲める「葛根湯」もあります ↓ 家族みんなで風邪のひき始めに備えられますね。